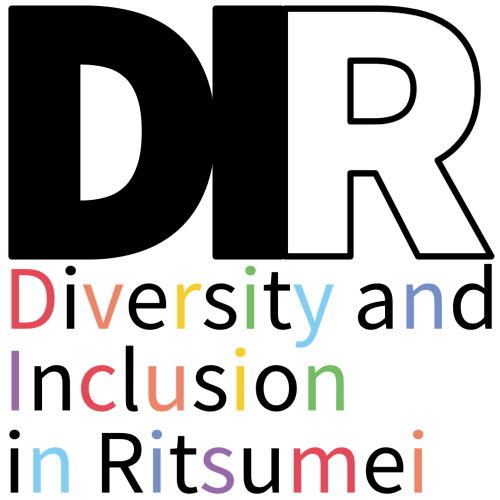Dir2024年度の活動は、下記のプロジェクト趣旨で、立命館大学のグラスルーツ実践支援制度の助成を得て行いました。
「キャンパス構成員によるトランスフォーマティブなダイバーシティ&インクルージョン推進プラットフォームの形成プロジェクト」
プロジェクト申請書より:
本プロジェクトは、ダイバーシティ&インクルージョンを実現する大学を、学生・職員・教員の内発的な問題提起と対話・学習・協働を通して一歩一歩着実に、そして創造的に実現していくためのプラットフォームの構築に挑戦し、多文化共生社会の実現に足元から取り組む姿勢、知識や能力、関係等の資源をキャンパス内に形成・蓄積するボトムアップのしくみづくりを目指す。
このような構想のきっかけとして、マイノリティとして大学生活を過ごしている学生達は大学の制度や授業等で日々問題状況に向き合っており、こうした学生達から本申請を行う教職員達に相談と問題提起があった。社会における多様性に対する差別・抑圧の現状を反映して本学にも今なお様々な問題が存在しているが、本学はこうした現状を真摯に受け止め、より良い社会をつくるモデルフィールドとして社会変化を構想・実現していく場でありたい。そのためには、本学構成員、特に学生が発した声をもとに、その声を聞いた他の学生も含めた学生・職員・教員がつながり、主体的に調査や討論を行い、D&I推進室と連携しながら、改善策を模索していくためのプラットフォームの形成が必要である。そこで、本プロジェクトは、ダイバーシティの具体的な焦点として、(1)エスニシティやルーツ(ルート)、(2)ジェンダーとセクシュアリティの2つの軸に注目し、国籍や民族的背景や移動の経験、また性に関わる生き方において、多様な(少数派の)背景を持つ学生が現在キャンパスでどのような経験をし、悩みを強いられ、またいかなる変化を希望しているのかや問題の背景を調査検証し、専門知や他大学等の先進事例を学び、本学における問題解決の方策を模索、提言する。また、こうした協働の過程で得られたデータ、気づきや視点、問題解決の展望やステップを学生主体で学内に発信するコンテンツの制作、および、FD研修に活用しうる資料を制作する。
本プロジェクトが取り組む問題状況の具体例として、日本生まれ育ちの多様なエスニシティやルーツ(ルート)をもつ学生が事務上「留学生」として処遇されてしまうという事態や、周囲の学生・教職員の無知や無自覚な差別が授業参加の妨げとなっている現状など、グローバル大学を掲げる本学が足元の構成員の多様性に対応していない実態がある。また、一橋大のアウティング事件に見られたようにLGBTQについて大学のすべての構成員が多様性を前提とした日常的なコミュニケーション能力等を獲得する必要があるにもかかわらず、本学におけるこうした学習や協働の機会は現状ではまだまだ限られている。一方、マジョリティの学生達の中にもこうした問題に主体的な関心を持ち、多くのことを学びながら問題の改善に関わりたいと考えている学生は少なくないが、そうした回路が存在していない。こうした現状に対し、自らのキャンパス空間の変革を志向する学生・教職員がつながり、多様性の表層的な賞賛にとどまらず真に多様性に開かれた大学をめざして身のまわりから地道な変化を模索していくためのグラスルーツなプラットフォームの形成は、R2030の掲げる多様な個が協働し自己変革する組織としての大学、そして学生に社会実装力を育む活動空間としての大学の実現に貢献する、自由な挑戦のしくみづくりの一環として、重要な取り組みとなる。 ……(後略)